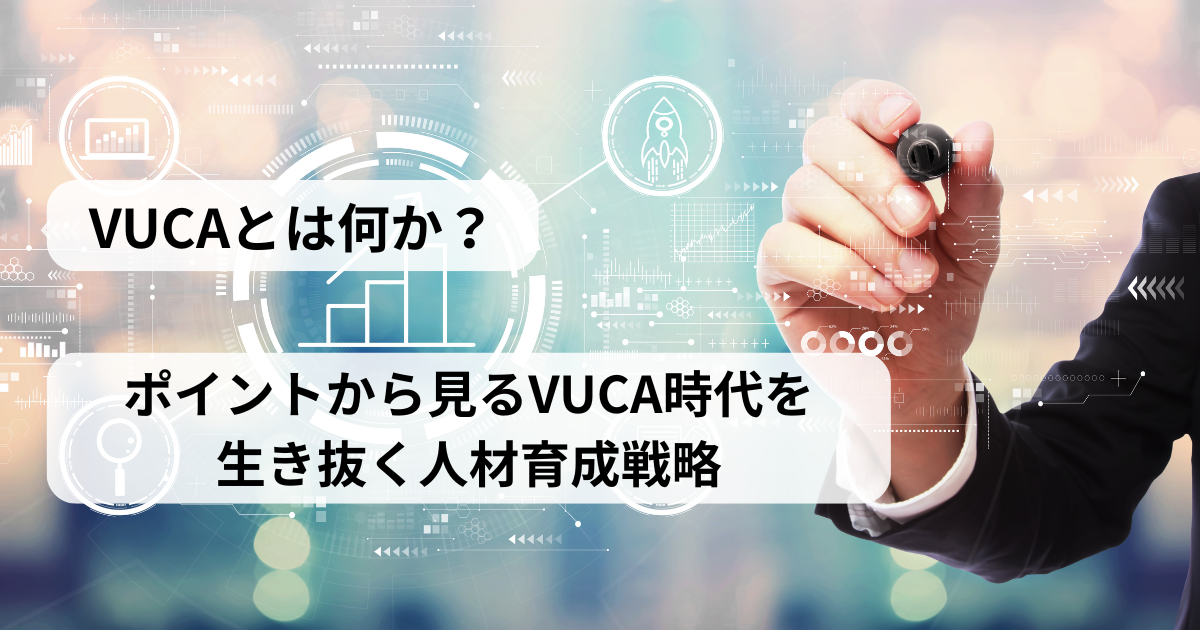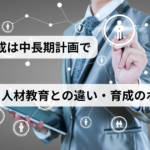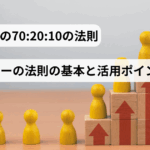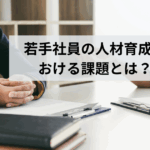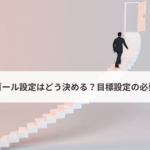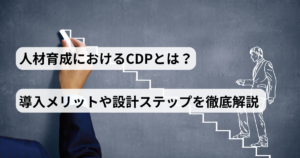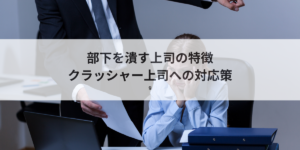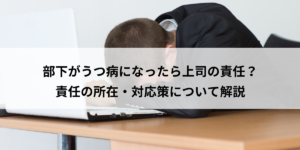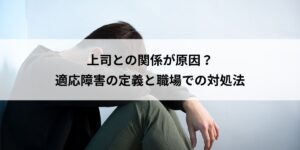「これまでの研修や評価制度が機能しなくなっている」
「変化の激しさについていける人材が少なくなったような…」
上記のようなお悩みはありませんか?現代は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれる、先行き不透明で予測困難な時代と言われています。
しかし、いきなり「VUCA時代が~」と言われても、そもそもの意味がよく分からないという方も少なくないでしょう。そこで本記事では、そもそも「VUCA」「VUCA時代」とは何か?予測困難な時代での人材育成には何が必要なのかについて詳しく解説します。
いろいろ試しているけれど、なかなか人材育成の成果が見えてこないとお悩みなのであれば、ぜひ最後までご参考にしてください。
「VUCA」 「VUCA時代」とは何か?
VUCAとは「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の4つの英単語の頭文字をとったものを指します。
それぞれの単語が示す意味のように、予測不能な現代が「VUCA時代」と呼ばれているのです。それぞれの意味をビジネスに絡めて深堀すると以下のようになります。
| 言葉 | 意味 |
| Volatility(変動性) | テクノロジーや市場ニーズが急速に、かつ広範囲に変化する様 |
| Uncertainty(不確実性) | 将来の予測が難しく、不確実な出来事が頻発する |
| Complexity(複雑性) | グローバル化や多様な価値観が絡み合い、問題が複雑化する |
| Ambiguity(曖昧性) | 何が正解か、原因と結果の関係さえも不明瞭になる |
昨今、AIの進化や地政学リスクの増大、消費者の価値観の多様化などにより、企業を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。企業経営を進めていく上で、「これまでの研修や評価制度が機能しなくなっている」「変化についていける人材が少ない」といった危機感を覚えている方も少なくないでしょう。
このようなVUCA時代において、企業が持続的に成長し、変化を生き抜くための鍵となるのが、より本質的・効率的な「人材育成」になるのです。
従来の育成モデルが通じなくなった原因
曖昧で予測不可能な時代に突入することで、なぜ、従来の研修や人材育成モデルに限界が来たと言われているのでしょうか?
主な原因として、終身雇用や年功序列が前提であった旧来型の育成モデルは、「安定した環境」と「明確な正解」があることを前提としていたからだとされます。例えば、以下のような育成モデルが挙げられるでしょう。
・知識、スキル偏重型の教育: マニュアルや過去の成功事例(安定した環境)に基づき、「正しい手順」や「必要な知識」を効率的に詰め込むことを目的とする
・OJT(On the Job Training)中心: 現場の先輩が過去の経験に基づいて(安定した環境)業務を教える(明確な正解)ことが中心で、既存の業務を正確にこなす人材を育てることに特化
・「正解」ありきの評価制度: 上層部が立てた
計画に対する達成度や、ミスがないかを評価(安定した環境・明確な正解)することが中心
多くの方にとって、身近な育成方法ばかりだったのではないでしょうか。しかし、VUCA時代では、環境が安定しているという前提そのものが崩壊しています。
新しいテクノロジーが次々に出現し、顧客のニーズも瞬時に変化する中では、人材育成の方法そのものも変わっていかなければならないのです。「今までこのやり方でうまくやってきたから」「すぐ新しいものに飛びつくだけが良いことではない」このような考え方は、現代では通じないと考えましょう。
VUCA時代に求められる人材の3つの能力
予測不能な時代を生き抜き、変化を成長の機会に変えるためには、社員一人ひとりに確かな力を身に着けさせる必要があります。
ここでは、特に必須とされる3つの能力について見ていきましょう。
変化を乗りこなす「適応力と学習能力」
VUCA時代に最も求められるのは、環境の変化に迅速に対応できる「適応力と学習能力」です。なぜなら、テクノロジーの進化や市場の変動が激しすぎるため、特定の知識やスキルがすぐに陳腐化してしまうから。従来の知識に固執していては、新しいビジネスチャンスを捉えることができないのです。
具体的には、長期間の計画を練るよりも、まずは小さく試行し、失敗から即座に学び、次の行動へとつなげるアジャイルな思考が必要だと言えるでしょう。また、過去の成功体験という固定観念を意識的に捨て去る「アンラーニング(学びほぐし)」が、新しい知識を取り込む際に有用になります。
そのために企業が社員に対し行うべきことは、新しいことを安全に試せる「学習する文化」を提供することだと言えるでしょう。
不確実性の中で価値を生み出す「問題設定力と創造力」
VUCA時代には、不確実な状況下で「解決すべき本質的な問い」を見つけ出す問題設定力が必須です。なぜなら、市場が曖昧で複雑化しているため、課題そのものが明確ではないからです。従来の「問題解決力」だけでは、問題は解決できたけれど、そもそも解くべき問題が間違っていたということになりかねません。
例えば、「売上低下」という結果に対し、「顧客の価値観の真の変化は何か」という本質的な問いを自ら見つける力を鍛えるなど。情報を鵜呑みにせず、クリティカル・シンキングで本質を見抜き、新しいアイデアを創造することが求められます。
企業は、指示待ちではなく「ゼロから課題を設計し、価値を生み出せる人材」の育成に注力すべきだと言えるでしょう。
複雑な状況を打破する「自律性と協働力」
VUCA時代の複雑な状況を打破するために、社員一人ひとりに「自律性」と「協働力」も不可欠になります。なぜなら、グローバル化やテクノロジーの進展により、問題が部門や国境を超えて複雑に絡み合ってくるため、トップダウンの指示や一人の天才の知恵だけでは解決が不可能になっているからです。
育成時に求められるのは、指示を待たずに自らの責任で最適な行動を判断するオーナーシップ(自律性)の力を底上げすることです。または、専門のアドバイザーと連携し、異なる価値観を柔軟に取り入れて新しい解決策を共創する力が求められます。
これらの実現に必要となるのは、企業が個人の当事者意識を高め、部門横断的なチームワークを促進する環境づくりに注力することです。
VUCA時代を生き抜く能力を劇的に引き出す3つのポイント
では、上記までで解説した3つの能力を社員から引き出すにはどのような方法があるのでしょうか?ここでは必要となる能力ではなく、能力を引き出すための3つのポイントについて解説します。
OJTから「OJD(On the Job Development)」へ
VUCA時代の人材育成は、OJT(訓練)からOJD(能力開発)へと目的をシフトする必要があります。その理由は、単に目先の業務スキルを教えるだけのOJTでは、将来の不確実な変化に対応できるリーダーとしての人材が育たないからです。
OJDでは、新入社員や若手に対し、将来のキャリアを見据えた目標を設定させ、現在の能力では解決できない難易度の高い課題を意図的に任せます。このことでOJTとは異なり、上司は答えを与えるのではなく、フィードバックを通じて能動的な成長を促す役割に変わります。 基本的に短期的な「訓練」ではなく、中長期的な「能力開発」を前提としたOJDへの転換こそが、変化に強い組織の土台を築いてくれるはずです。
「自律的な学び」を促す仕組みの構築
企業が教え込むのではなく、社員自身が学びたいときに学べる「自律的な学び」の仕組みも必要です。なぜなら、現代は環境変化が速すぎるため、企業側の固定的な研修では知識がすぐに陳腐化してしまうから。変化に追いつくには、個人の主体的なアップデートが不可欠になるのです。
具体例を挙げれば、個人の目標に合わせたeラーニングや、社外経験を得る越境学習の推奨などになります。これらにより、社員は自分に必要なスキルを最適なタイミングで獲得できるようになるでしょう。
企業がすべきことは学習機会をパーソナライズすること。あとは、社員が自発的に成長し続けられる環境を試行錯誤しながら整えていくことになります。
リーダーシップのあり方の転換
VUCA時代を生き抜くには、マネジメント層のリーダーシップを「指示・命令型」から「支援・コーチング型」へ転換する必要があります。なぜなら、不確実で複雑な状況下では、現場の最前線にいる社員の自律的な判断と行動が不可欠であり、トップダウンの指示系統ではスピードが追いつかないからです。
基本的にリーダーはメンバーに「答え」を与えるのではなく「問い」を投げかけるコーチングを徹底し、サーバント・リーダーシップでメンバーの挑戦を支援します。マネージャー自身が、部下の自律性を引き出すスキルを学ぶリスキリングが重要になるでしょう。
したがって、リーダーは「部下を育てる人」から「部下が育つ環境を整える人」へと役割を変えていくのです。
まとめ
VUCA時代は、確かに企業にとって前例のない脅威です。しかし同時に、従来の慣習やしがらみから抜け出し、組織構造やビジネスモデルを抜本的に見直す「最大のチャンス」ともいえるでしょう。
この激しい時代の変化を乗り越え、持続的に成長し続ける組織の土台は、社員一人ひとりの「自律性」と「学び続ける姿勢」が必須になります。人材育成を「マイナスのコスト」ではなく「未来への戦略的な投資」と捉え直すときが来ているのです。
ただ、すべての企業が人材育成に力を入れられるわけではありません。それどころか「金銭的コストより人的リソースが乏しくて育成に力を入れられない…」と臍を噛む思いをしている経営者の方も多いでしょう。 そのようなときは、自社内で完結させるのではなく、外部の力をうまく活用していきましょう。当社の異業種交流階層別研修『錬成講座』は、主体的に考え実践することを様々な面から学べます。講座終了後も3か月のフォローアップを実践、着実に力をつけるお手伝いをいたします。