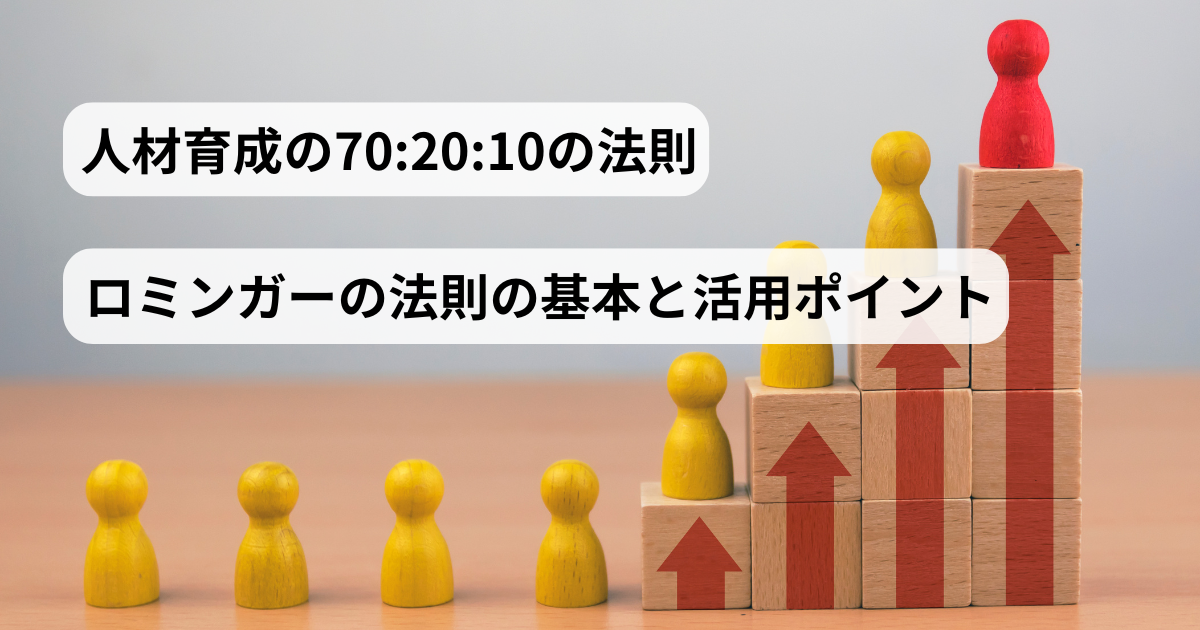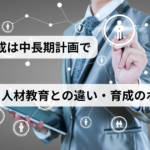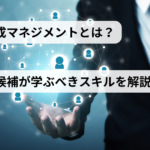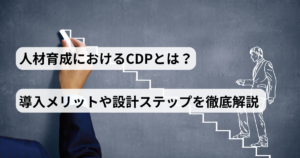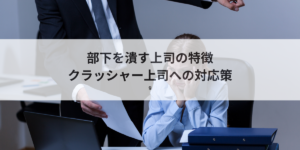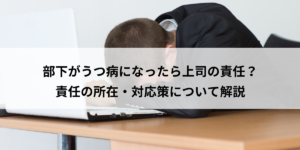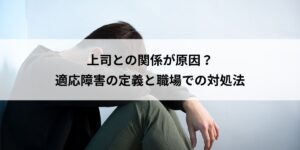「人材育成の70:20:10の法則とは?」「法則をどうやって実際の人材育成に活かせばいい?」などと悩んでいませんか?
人材育成の70:20:10の法則とは、人の成長に影響を与える要素が「70%が業務経験」「20%が薫陶」「10%が研修」という比率で構成されるという考え方です。この法則を理解することで、バランスの取れた効果的な人材育成プログラムを設計できます。
本記事では、70:20:10の法則の基本概念から、各要素を最大限に活用するための具体的な方法について解説します。導入の流れや活用する際の注意点も詳しくまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
人材育成の70:20:10の法則とは?
人材育成の70:20:10の法則は、人の成長に影響を与える要素の割合を示した実践的な理論です。『ロミンガーの法則』とも呼ばれており、アメリカの研究機関「CCL」が実施した調査から生まれた法則になります。
『ロミンガーの法則』とも呼ばれる成長の比率
人材育成における70:20:10の法則は、「ロミンガーの法則」とも広く呼ばれています。1990年代にアメリカの人材開発企業「CCL(センター・フォー・クリエイティブ・リーダーシップ)」の研究者であるモーガン・マキャラックとマイケル・ロミンガーによって提唱されました。
人の成長に影響を与える要素の割合として、以下の要素別で比率を振り分けています。
| 学習要素 | 比率 | 内容 |
| 業務経験 | 70% | 実務を通じた経験、挑戦的な業務、問題解決など |
| 薫陶 | 20% | 上司や先輩からの指導、フィードバック、メンタリングなど |
| 研修 | 10% | 公式な研修プログラム、セミナー、読書、eラーニングなど |
ロミンガーの法則は単なる数値の比率ではなく、効果的な人材育成には実践と対話などをバランスよく組み合わせる必要がある点を示す指針です。
法則が生まれた背景
法則を生み出した研究者たちは、成功した経営者に対して「あなたの成長に最も影響を与えたものは何か」と質問し、今回の比率を導き出しました。今回の研究は、従来の研修中心の人材育成に疑問を投げかけ、実践的な経験の重要性を科学的に示しています。
当時は企業の人材育成が座学中心だったため、研究での発見は画期的でした。法則は発表後、グローバル企業を中心に広く受け入れられ、人材育成の基本的な考え方として定着しています。
現在では、多くの企業が人材育成戦略の基盤として活用し、実践と対話を重視した総合的な人材育成アプローチを採用しています。
70%の「業務経験」を設計する方法
効果的な人材育成には、業務経験を意図的に設計することが不可欠です。単に日常業務をこなすだけでは70%の学習効果は得られず、成長につながる挑戦的な経験を計画的に提供する必要があります。
具体的な設計方法は以下の通りです。
- 意図的な経験機会を生み出す
- キャリアビジョンに基づいた実務経験を積む
- 失敗から学ぶ機会を提供する
詳しく解説します。
意図的な経験機会を生み出す
人材育成において効果的な業務経験を提供するには、日常業務の中に意図的な学びの機会を組み込む工夫が必要です。通常業務をこなすだけでは真の成長は限られるため、現在の能力よりやや高いレベルの課題に挑戦させる「ストレッチ経験」を計画的に設計することが重要です。
経験機会の例として、新規プロジェクトへの参画や異なる部署との協働作業、通常より大きな責任を伴う業務の担当などが挙げられます。経験機会を生み出す際には、単に難しい仕事を与えるだけでなく、経験を通じて何を学んでほしいかという育成目標を明確にすることが大切です。
上司は部下の成長段階を見極め、適切なタイミングで適切な難易度の経験を提供すれば、効果的な学びを得られます。
キャリアビジョンに基づいた実務経験を積む
人材育成では、個人のキャリアビジョンと連動した実務経験の設計が重要になります。将来なりたい姿を明確にし、到達するために必要なスキルや経験を特定した上で、計画的に実務経験を積むアプローチが効果的です。
例えば、将来マネジメント職を目指す人には早い段階からチームリーダーの役割や予算管理の一部を任せたりする経験が有効です。定期的なキャリア面談を通じて個人の志向を把握し、組織のニーズにあう形で経験機会を提供すれば、双方にとって価値ある成長が実現します。
失敗から学ぶ機会を提供する
人材育成において、失敗経験は貴重な学びの機会です。失敗しても大きな問題にならない環境で挑戦させれば、実践的な問題解決能力を習得できます。
失敗から学ぶ機会を提供するには、心理的安全性の確保が前提条件です。失敗を責めるのではなく、「何を学んだか」に焦点を当てる組織文化を構築すれば、メンバーは萎縮せずに挑戦できるようになります。
20%の「薫陶」を活用する人材育成のポイント
人材育成における「薫陶」とは、上司や先輩からの指導や助言、フィードバックを通じた学びを指します。20%の要素は、70%の業務経験から得た学びを深め、意味づけする重要な役割を果たします。
「薫陶」を活用する人材育成のポイントをまとめると、以下の通りです。
- 成長を促す対話の場を設ける
- 多様な視点からのインプットを得る
- 学びの場を意図的に生み出す
詳しく解説します。
成長を促す対話の場を設ける
人材育成において、成長を促す対話の場を意図的に設けることが大切です。単なる業務連絡や指示出しではなく、思考を深め、気づきを促す対話が人の成長を加速させます。
効果的な対話の場としては、定期的な1on1ミーティングやプロジェクト後の振り返りセッション、キャリア開発に関する面談などが挙げられます。話し合いの場では、「どう思う?」「他にどんな方法が考えられる?」といった質問を通じて、相手の思考を促進することが重要です。
多様な視点からのインプットを得る
多様な視点からのインプットを得ることは、人材育成において思考の幅を広げ、創造性を高める重要な要素です。単なる上司からの指導だけでなく、様々な立場や専門性を持つ人々との交流を通じて、多角的な視点や考え方を吸収できます。
例えば、若手社員が複数の先輩社員からアドバイスを受ける機会を設ければ、多様なアプローチや考え方に触れることが可能です。多様なインプットを得るためには、組織として部門や階層を超えた交流の機会を意図的に創出することが重要です。
異なるバックグラウンドを持つ人々との対話は、自分では気づかなかった視点や発想をもたらし、成長を加速させます。
学びの場を意図的に生み出す
人材育成において、日常業務の中に学びの場を意図的に生み出す施策は重要な戦略です。通常の業務フローの中に、対話や振り返りの機会を組み込めば、継続的に学習する環境を生み出せます。
例えば、週に一度のチームミーティングの最後に「今週学んだこと」を共有する時間を設けるだけでも、学びの意識が高まります。リモートワーク環境でも、オンラインツールを活用して学びの場を創出することが可能です。
10%の「研修」を最大限活用するポイント
人材育成における「研修」は全体の10%を占めるものの、残りの90%を支える重要な基盤です。研修を通じて体系的な知識やスキルを習得すれば、実務経験や薫陶から得る学びをより効果的なものにできます。
「研修」を最大限活用するポイントをまとめると、以下の通りです。
- 実務に直結する知識を効率よく習得する
- 参加型学習による知識の定着率向上を目指す
- 学びを実践につなげる環境を構築する
詳しく解説します。
実務に直結する知識を効率よく習得する
限られた研修時間を最大限に活用するためにも、実務に直結する知識を効率よく習得することが大切です。現場で即座に活用できる実践的な知識や、スキルに焦点を当てた研修設計が学習効果を高めます。
例えば、営業研修であれば実際の商談シーンを想定したロールプレイを行えば、学びの実用性が高まります。効率的な知識習得のためには、研修内容を業務レベルや役割に応じてカスタマイズすることも重要です。
一律の内容ではなく、参加者の現状と課題に合わせた内容を提供すれば、無駄なく必要な知識を習得できます。
参加型学習による知識の定着率向上を目指す
人材育成において、参加型学習は知識の定着率を大幅に向上させる効果的な手法です。一方的な講義形式よりも、受講者が主体的に発言して実践する機会を多く設ければ、学びの質と記憶の定着が高まります。
参加型学習の具体例としては、グループディスカッションやケーススタディの分析と発表、ロールプレイングなどが挙げられます。リーダーシップ研修では講義だけでなく、実際のチーム課題に取り組む演習を通じて、理論を実践に落とし込む経験を提供する方法が効果的です。
学びを実践につなげる環境を構築する
人材育成において、研修で得た知識やスキルを実務に応用できる環境を構築することが、学習効果を最大化する鍵となります。研修内容が実践されなければ、すぐに忘れられてしまうため、職場での実践と定着をサポートする仕組みが必要です。
学びを実践につなげるためには、研修後のフォローアップが重要です。研修で学んだ内容を実践するアクションプランの作成や定期的な進捗確認、実践時の課題解決サポートなどを通じて、知識の定着と実務への応用を促します。
人材育成70:20:10の法則を導入する流れ
人材育成に70:20:10の法則を導入するには、段階的なアプローチが効果的です。具体的な流れをまとめると、以下の通りです。
| 導入ステップ | 主な取り組み内容 | 期待される効果 |
| 1. 現状分析 | 既存の人材育成施策の70:20:10バランス評価 | 課題の明確化と改善方向性の特定 |
| 2. 施策設計 | 経験機会の創出、薫陶の仕組み構築、研修の見直し | バランスの取れた育成プログラムの構築 |
| 3. 管理職の理解促進 | 70:20:10の考え方や実践方法の研修実施 | 日常の人材育成における役割の明確化 |
| 4. 段階的導入 | 部門や階層ごとの優先順位付けと段階的実施 | 混乱を最小限に抑えた円滑な導入 |
| 5. 効果測定と改善 | 定期的な効果測定とフィードバックの収集 | 継続的な改善サイクルの確立 |
70:20:10の法則を導入する際には、単なる研修改革ではなく、人材育成の考え方そのものを変革する取り組みとして位置づけることが重要です。特に計画的な経験付与の仕組みづくりが鍵となります。
人材育成70:20:10の法則を活用する際の注意点
人材育成70:20:10の法則を活用する際には、以下の点に注意しましょう。
- 固定的な数値として捉えない
- 新しいスキル習得時には研修の比重を高める
- 組織や業種の特性に合わせてカスタマイズする
詳しく解説します。
固定的な数値として捉えない
人材育成70:20:10の法則を活用する際には、数値を厳密な比率として捉えるのではなく、学習と成長の原理原則として理解することが重要です。実際の最適な比率は、個人の学習スタイルや職種、キャリアステージによって異なります。
例えば、新入社員や未経験の分野に取り組む場合は、研修の比率を一時的に高めることが効果的な場合があります。各要素ごとに得られるものと相互関係を認識し、状況に応じて柔軟に適用することが大切です。
新しいスキル習得時には研修の比重を高める
人材育成70:20:10の法則を実践する際、新しい分野やスキルの習得段階では、研修の比重を一時的に高めることが大切です。未知の領域に足を踏み入れる際には、基本的な知識やフレームワークを体系的に学べば、学習の質が大幅に向上します。
例えば、新しいシステムやツールの導入時には集中的な研修を行い、基本操作を習得してから実務に適用すれば効率的な学習が可能になります。管理職に初めて就く社員には、マネジメントの基礎理論やコミュニケーションスキルに関する研修を先行して提供する方法が有効です。
基礎知識を習得した後は、徐々に実践経験の比率を高めていく必要があります。
組織や業種の特性に合わせてカスタマイズする
製造業やサービス業など、業種によって求められるスキルや学習方法は大きく異なるため、画一的な比率適用は適切ではありません。例えば、高度な専門知識が求められる研究開発部門では、研修や自己学習の比率を高めた方が効果的な場合があります。
一方、顧客接点の多い営業部門では実践経験と先輩からのフィードバックの比率を高めれば、より効果的な育成が可能になります。すでに確立された研修プログラムがある組織では、プログラムを活かしながら経験学習の要素を強化するアプローチが現実的です。
まとめ
人材育成70:20:10の法則は、人の成長に影響を与える要素の割合を示した実践的な理論です。法則を活用する際には、単なる数値目標ではなく、人材育成の原理原則として捉えることが重要です。
特に10%の研修時間は、残りの90%を支える重要な基盤となります。リーダーとして人材育成で成果を出すためには、10%の時間を確保し、質の高い研修に投資することが不可欠です。
株式会社日本経営開発研究所が提供する「次世代経営者錬成講座」は、リーダーとしての成長を促進するプログラムです。異業種の次世代リーダーとの対話や実践的な課題解決を通じて、残りの70%の業務経験と20%の薫陶をより効果的なものにする基盤を構築します。
企業の持続的成長と競争力強化に向けて、次世代経営者錬成講座への参加を検討してみてはいかがでしょうか。経営幹部候補者を見つける絶好の機会となるため、まずはお問い合わせください。