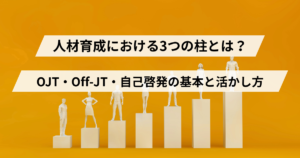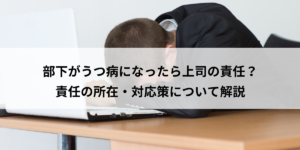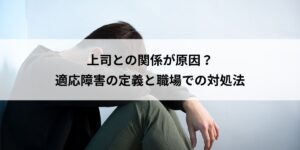第1部 現代企業の経営理念
第2章 日本的経営理念のあり方
第1節 日本における企業と従業員の関係
第1章では、現代企業の経営理念を考えることによって、企業と従業員との関係について基本的な事実を明らかにしてきた。すなわち、「付加価値志向の経営」のもとでは、「分配においては一時的に対立する面はありながらも、付加価値の効率的な増大=生産性の向上では労使が協力することが双方の利益である」ということである。これは、体制の違い、国の違いをこえた基本的な事実にほかならない。
これをふまえて、第2章では、日本における企業と従業員の関係についての基礎的な事実を明らかにする。日本における企業と従業員の関係を明らかにするためには、日本的経営の特質を知らなければならない。
過去を振り返れば1980年代の前半、日本経済=日本企業の国際競争力の強さが欧米でも注目され、そのなかで「日本的経営」の強さが脚光を浴びることになった。
一方、バブル崩壊後の日本の経済は低成長が続き、それとは対照的にアメリカの経済がめざましい活力と成長力を見せる中で、今は「日本的経営」の弱さが注目されている。
しかし、このような多分にムード的な「日本的経営賛美論」や「日本的経営悲観論」は、科学的検討に耐ええないものが大半である。とくにこのようなムード的議論では、日本的営を特徴づけ基礎づける終身雇用制を、なにか「経営政策」(採用することもやめることもできる方策)であるかのように考える傾向が支配的であるが、これはまったく誤った議論である。終身雇用(封風的労働市場を基盤とする)は、「経営方策」ではなく、経営の意思によっては左右されない「雇用慣行」であり、「社会制度」である、という社会科学的識が、日本的経営を正しく認識する大前提である。
企業規模の大小とか、技術力の優劣といった、いわば「量的な差異」をこえた、欧米(とくにアメリカ)と日本の経営との「本質的な差異」は、どこにあるか。結論的にいえば、それは経営の前提となる「労働市場の差異」に求められる。
アメリカでは「職務ごとに、労働の需給に応じて、企業間、あるいは企業の内外を労働力が移動する」横断的労働市場が形成されている。日本とは異なり、アメリカでは、企業間を労働力が比較的自由に移動する。すなわち、転属車が高い(一般的には、ホワイトカラー、ブルカラーを問わず三〇名前後)。あるいは、不況になれば、解雇は容易に行なわれる。いったん解雇されても、好況になれば再び同じ企業に就職する。企業内外の移動といったのはこのことを示す。自動車産業を例にとれば、フォードが不振でGMが好調なときには、フォードの労働者はGMに収引される。あるいは、自動車産楽が不況で不振になれば、大量の失業者がでることになる。その失業者も、再び好況がくれば、吸引される。解雇・就職、転職・中途入社という、労働力の移動が、比較的自由に行なわれるのが、アメリカの労働市場の特徴である。
このような労働市場のあり方は、日本では考えられない。日本では大企業の基幹社員を中心に終身雇用が慣行として定着している。転職・中途入社は、ふつうの場合は不利をともなう。不況であっても、基幹社員の解雇は、よほどの企業の危機でないかぎり、基本的にはありえない。一部の職人層や一一般職・補助職については短期雇用が多いといえるが、基幹的な従業員は、終身雇用が支配的なのである。
日本でも、明治期には、職員層は「生涯奉公」として終身雇用的であったとはいえ、当時の工員層は、短期雇用がふつうで労働移動もひんぱんであった。工員層が、終身雇用へ向かって一歩すすんだのは、日露戦争から第一次大戦のブームにかけて、日本の機械工業・重工業が一定の発達をみせた段階での熟練工不足→「子飼い」の基幹工養成の必要が要因となっている。この傾向は、第二次大成に向かう戦時経済下の重工業の発展と労働力統制によっていっそう促進された。このような戦前での進展のうえにたち、戦後の職員工員を一体とした企業内組合の成立、そのなかでの、労働者の地位向上によって、終身雇用制は、確固として、ゆらぐことなき労使慣行として、日本に定着したのである。
欧米では労市場が「横断的」なかたちをとっている。被雇用者は、ある職務について自己の能力を発揮し、しかるべき報酬をうるために求職する。また企業は、ある職務を遂行するために人材を求めればこそ求人する。被雇用者は、職務を遂行しながら正当な報酬の相場がえられなければ退職し、他企業に転職する。企業側も、ある要員が職務遂行能力不足であると評価すれば、解雇する。
日本では、欧米との対比でいえば、基幹社員に関しては労働市場が「封鎖的」である。被雇用者は原則として新規学卒者にかぎられる。新規学卒者は、ある職務について自分の能力を発揮するために求職するのではない。一生をそのなかで送るにふさわしいと思う「企業」を求める。企業も、採用者の潜在能力・人柄を期待するのである。
このような、一方における「横断的労働市場」、他方における「封鎖的労働市場」という差異こそ、経営の人的条件を左右するものであり、日米間の経営の本質的な差異を形づくっているのである。
以上の本質的な差異から、企業と従業員の関係を考えるうえでの、種々の日米間の差異がでてくる。
《第一》には、管理職と作業員の関係の差異である。欧米では、職務の必要がまずあって、人がその職務の遂行能力を十分もつことを前提に仕事をすることになる。職務を大きく区分したとき、最大の区分は、管理職と作業員(労働者)の区別である。欧米は、大卒・大学院卒の管理職候補は、当初から管理最アシスタントとして管理層に所属することになる。この層は当然、非組合員であり、管理最候補たる管理職アシスタントはそもそものはじめから組合員ではない。他方、作業職として企業に入る人はそれ以後も、企業のなかで地位を管理職層へと上昇させることはない。日本のようないわゆる年功的要素の付加はまったくないから、何十年勤続しようと、入社当時と同じ現場の職務をつづけていることは例外ではない。むしろふつうだといってもよいくらいである。作業員の人が、管理層にまで上昇することは、企業外で並みはずれた努力をして職務遂行能力を習得し、それが企業に評価されないかぎり、ありえないことである。そして、労働組合は、排他的に、作業職につく人々(労働者、worker)によって構成されている。
すなわち、欧米では、そもそも、入職する当初から、作業員と管理職、作業層と管理層は、はっきりと区別されているのであり、それ以降も基本的には変わることのない、固定的な階層として区別されているのである。そして労働組合は、作業職によってのみ占められている。
したがって、欧米では「経営者・管理職層」と「労働者・作業職層」とが、固定的な「階層」をなしており、その意味で、階層格差が存在しているといってよい。そして労働組合は、この階層格差を前提とした「労働者・作業職」の組織として存在しているのである。
むろん、ここにいう階層というのは、マルクスのいうような意味での(つまり生産手段の所有、企業の所有によって階級を区分するという意味での)階級ではない。そのような階級概念が成り立ちえぬことはすでに指摘しておいた。ここでの階層とは、ふつうの社会学で使っている意味での階層、すなわち、「容認にこえられぬ壁をもった固定的な社会グループ」といった意味での階層である。この意味での階層的区別が欧米では明瞭なのである。
これに対し、日本では、特定職務の遂行能力をただちに期待されて入社することはない。大卒・高卒、技術職・事務員という大まかな区分はありながら、むしろ「よき従業員」たる潜在能力・人柄が期待されているのである。たとえ将来の企業のトップとなるような人材でも、入社当初は、平の従業員であり、したがって、企業内組合の組合員なのである。平の従業員が、さまざまの職務を送行しながら、下から上へ、同一企案内で地位を上昇させ、管理層へと昇っていくのである。非常に有能な人材で、将来、最短距離でまちがいなく幹部に登用できる人材でも、やはりはじめは組合員である。
また終身雇用制であるということは、定年までの長期勤続にともなう継続的な能力向上の累積を必々とする。そうでなければ勤続を重ねる直味がない。それゆえ、作業員の人が、定年まで、入社当時と類似した職務を巡行しているということは本来ありうべからざることであって、作業員の人も勤続とともに必ず能力を向上させその地位を上昇させるのでなければならない。若年では作業員だった人が非組合員たる管理職の地位まで到達することは、大企業でも珍しくない。中堅企業以下ではむしろふつうとさえいえる。
日本では、一方では、トラブ候補生も当初は組合員であり、他方では、作業職従事者も年とともに管理層へ上昇する。そのような意味で、日本には、欧米のごとき固定的な社会的グループとしての階層は認められないのである。もともとは組合員で、労働者層(階級)であったものが、三〇年後には経営者層(階級)になる、というようなことでは、通常の意味における「階級」という言葉が意味をなさぬことになるのは明らかであろう。
日本の経営では、経営陣・管理層と労働組合員の関係は、欧米のようにはっきりと区分された固定的グルーブを意味するのではなく、むしろ同一企案の従業者という枠のなかでの「立場の違い」としてとらえられねばならない。
《第二》には、労働組合の組織ならびに行動の差異に注目しなければならない。
横断的労働市場を前提とする欧米では、産業別労働組合が、労働組合の基本的な組織形態となる。職務ごとに労働者が移動するのは、ふつうは、一産業の範囲である(紡績工が自動車産業へ移ってプレス工になるということは基本的にはない。そのようなときには、未熟練の職種についてしまうことになり、賃金の低下は退けられないからである)。したがって、欧米の労働組合は、一産業を包括する必要がある。
この産業別労働組合の行動様式は、基本的には、労働力の価格をなるべく高く売ることに尽きる。横断的労働市場のもとでは、職務ごとに賃金の相場が形成されている。たとえば、単純反復的職務では、週給四〇〇ドル、というように、年齢・勤続にかかわりなく職務に応じた賃金の相場がある。したがって、労働力の売買は、物の売買に似てくる。労働組合は、労働力の「売手独占」という立場で、労働力の「市場価格」=相場をつりあげることに関心を集中する。欧米の組合は、これが主であるといってもよい。欧米の組合にとって団交 (collective bargaining)は、文字通りの交渉=取引(bargaining)なのである。
それゆえ、非常に特做的なことは、欧米の組合は、解雇にさしたる抵抗をみせないことである。なぜなら、不要な労働力をムリに企業に買わせれば、必ずや労働力のたたき売り、濫売にならざるをえないからである。ただし解雇の際には、一応労使慣行上のルール(先任権ルール)があって、先任者に優先権が設定され、勤続の短い順に解雇されるという場合が多い。その代わり、欧米の産業別労働組合は「労働力の売手独占」組織にふさわしく、転職のあっせんもするし、失業期間の保障もするのである《国家の失業保険と並行して)。
賃金水準は、以上のように、職務ごとに産業別相場として決定される。個々の企業の業績とは無関係である。もし同一の最務で企業ごとに賞金格差があれば、労働移動を通じて、賃金は平準化される。それゆえ、国々の企業の業績がよかろうと選かろうと、賃金交渉は、産業の相場として決定されることになる。
これに対し、封鎖的労働市場を前提とする日本では、労働組合は、基本的には、企業別労働組合(企業内組合)という組織形態をとることになる。たしかに、日本の労働組合でも、一応、産業別組合の「名称」はもっているものもある(いわゆる早産である)。しかしこれは、企業別組合の中央協議機関にすぎない。労働組合活動を左右する事項の決定権(加盟・除名権、スト権など)は、企業内組合にあるのが通例である。
日本では、欧米のような、職務ごとの労働移動や賃金相場があるわけではない。賃金にしても、より広い処遇全般にしても企業の業額に大きく左右される。業績に応じた処格差があっても欧米のように労働移動を通じて処遇が平準化されることがない。したがって欧米のように、個々の企業の業績とは一応区別されて、産業レベルの団体交渉で賃金相場が決まるということもない。企葉の業績が、貨金水準をも大きく規定してくるのである。企業が繁栄すれば、賃金・賞与昇進などすべての面で、従業員は有利になる。それゆえ、日本の組合では、企業業績の向上のために協力することが、労働組合の本来の目的たる「従業員の経済的地位の向上」のためにも、合理的な行動となるのである。欧米のように「労働力の売手独占」として労働力を高く売りつけることに行動を集中することを、組合活動の基本路線とすることはできない。そもそも「売手独占」の強みを発揮するには、それだけ労働市場が、本来の商品市場に近い状態になくてはならない。日本では、このような条件はないのである。
もし企業が衰退へ向かったり、極端な場合倒産したりすれば、終身雇用の慣行からして転職には非常な困難と不利を覚悟しなければならないのであるから、従業員の生活向上をめざす労働組合としては大問題である。そこで、企業業績が悪化すれば、まず雇用確保、企業業績の好転を第一に、賃上げなどは二の次、場合によっては賃金カットもやむなしという行動を、労組組合はとらざるをえない。この点、雇用確保よりも、賃金の維持・上昇を優先する欧米の産業別組合の行動とは、きわめて対照的である(日本の労働組合の中央協議機関(上部団体)などは、欧米の産業組合とは異なり、解雇された失業者にはなんらの補償(失業保険・転威あっせんなど)をもなしえない)。
以上、述べてきたように、日本と欧米では、労市場の型(タイブ)の本質的な差異、すなわち、程官の人的条件の根本的な違いから、企業と従業員の関係・労使関係についても、非常な相違がみられるのである。