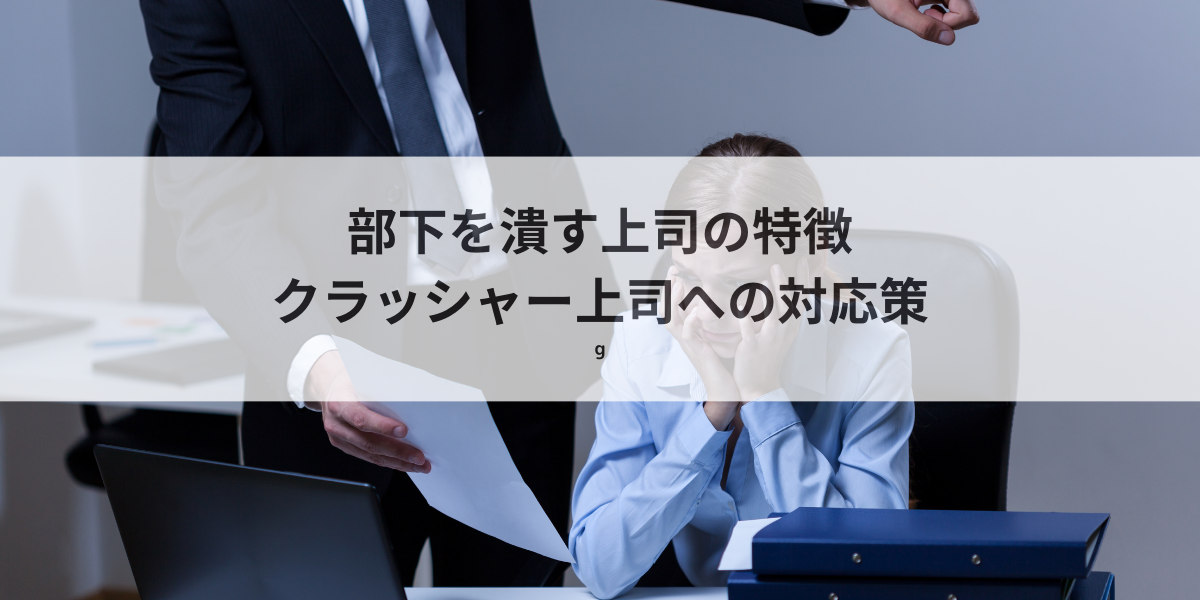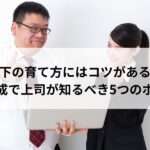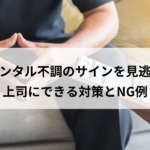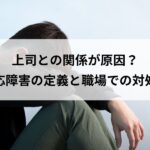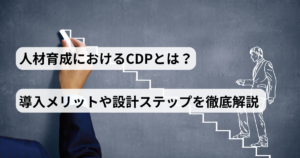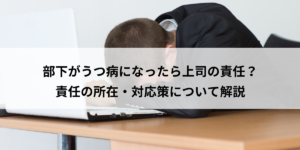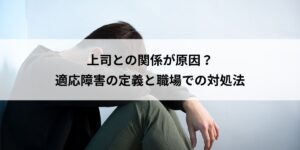部下を潰す上司とは、文字通り部下の適切な育成を行えず、メンタルの不調を招いたり退職させたりする上司を指します。
従来の上司といえば、まさしく管理職として部下の「管理・育成」が主な業務内容でした。しかし昨今では、管理職の肩書を持ちつつも実行者としての働きを期待されるシーンも増えています。
業務内容が増えたことから、適切な部下の育成を行う時間が限られるケースも多いでしょう。多くの管理職が苦慮しつつ時間を捻出する中、一部では「仕事はできるが部下を潰す上司」も出てきています。
では実際のところ「部下を潰す上司」にはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では部下を潰す上司に見られる特徴や周囲への影響、企業ができるクラッシャー上司への対応策まで詳しく解説します。
部下を潰す上司に見られる4つの特徴
まずは部下を潰す上司に見られる4つの特徴を見ていきましょう。特徴を把握しておくことで、いち早く問題がある上司を発見できるようになります。
共感性が低く鈍感
部下を潰す上司に共通してみられる特徴の中でも、特に顕著とされる点が「共感性の低さ」もしくは「他者の感情や表情に鈍感」なところです。
共感性が低い、または他者の感情に鈍感なため、部下が落ち込んでいてもなぜ落ち込んでいるのかが理解できません。また他者の感情を理解できないからこそ、自分が思っていることをオブラートに包むことなくストレートに発します。
配慮のない言葉をかけられれば、人は落ち込んだり、とっさに怒りを感じたりもするでしょう。しかし部下を潰す上司は共感性が低いため、なぜ部下が上記の感情に至ったのかを理解できないのです。
逆に「この程度の言葉で落ち込む(怒る)ようでは、社会人として半人前だ」と感じることもあるでしょう。自分が悪いことをしたという認識がないため、同じようなミスを繰り返しがちです。
自分が正しいという気持ちが強い
部下を潰す上司は、自分の行いや考えに強い自信を持っています。仕事を成功させるうえである程度の自信は大切なものです。しかし部下を潰す上司の場合、自分が正しいという気持ちが強すぎるため、自分の意見に反対するものを敵視しがちです。
そして「自分こそが正義だ」という考えが根底にあるため、敵視した相手への攻撃に容赦がありません。
また自分が正しいという考え方は、業務においても相手に自己流のやり方を押し付ける結果になりがちです。柔軟な思考を持つ部下であれば、やり過ごしたり都度指示を与えてくれることでやりやすくなったりもするでしょう。
しかし自分なりのやり方を模索したいと考える部下にとっては、非常に相性が悪い上司になります。
私情を挟む傾向があり感情的
仕事に私情を挟む、併せて感情的になって必要以上に強い言葉を使う点も特徴です。なお、私情を挟むのも感情的になるのも、基本的に部下を相手取ったときである点が大きな特徴だといえます。
自分より立場が弱いものや発言権が少ない相手を選んで、自身のストレスをぶつけているのです。
特に感情的になったり声を荒らげたりする行為は、業務を進める際の障害にしかなりません。攻撃を向けられた部下だけではなく、チーム全体の指揮に影響を与えるでしょう。
常に上司の動向を気にして、いつ不機嫌になるのかと首をすくめるような状態が続くことも考えられます。これでは各々が自由に仕事を行うことができないため、攻撃対象にされた部下はもちろん、チーム全体のモチベーション低下を招く原因になるのです。
仕事ができるor要領がよい
部下を潰す上司はおおむね「仕事はできる」という特徴もあります。実際に成果を出しているからこそ、部下を潰す上司でありながら降格や異動が難しい点に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
なお部下を潰すが仕事ができる上司は、以下2つのケースに分けられます。
- 業務の進行を第一にしているからこそ、部下の育成やメンタルに目を向けないケース
- 実際に仕事ができるのではなく、要領の良さから出世しているケース
どちらも問題がある上司といえますが、2の場合は本当に仕事ができるのか怪しい面もあります。部下を潰す上司への対策を考える場合は、どちらのケースなのかを慎重に見極めることも大切です。
部下を潰す上司の放置は悪手!想定される影響は?
部下を潰す上司を放置すると、企業にはどのような悪影響が出るのでしょうか?日々の業務が忙しいからと、放置しないためにも正しく影響を把握しておきましょう。
部署内の雰囲気が悪くなる
部下を潰す上司の中には、突然声を荒らげて部下を罵倒するような人もいます。実際に罵倒を受ける部下にしてみれば「次は何で怒られるのか…」とどんどん委縮してしまうことでしょう。
またいつ感情を爆発させるのか分からない人がいる部署であれば、周囲の人も健全に仕事を行うことが難しくなります。部署内の雰囲気をこれ以上悪くしないため、業務よりも上司の動向を気にするようになってしまいます。
部署内の雰囲気が悪くなるとともに、生産性低下の恐れも考えられるでしょう。
人材が育たない・人材流出で人手不足に
部下を潰す上司は基本的に適切な人材育成ができません。人材が育たないどころか、潰されてしまった部下はメンタルを病んだりすることで、退職を選んでしまうこともあるでしょう。
問題のある上司を放置すると、潰された部下が会社を退職してしまうことが繰り返されます。また潰された部下を見ている周囲も、自分に被害が来ないようにと転職を考え始めてしまうでしょう。
優秀な人材の流出が起きてしまえば、企業にとって大きな痛手になります。
部下を潰す上司に企業上層部ができること
では実際に部下を潰す上司へ対策を行うとすれば、どのような方法があるのでしょうか。ここでは部下を潰す上司から部下を守る方法、併せて適切な育成を促すための対策について解説します。
社内アンケートを実施
企業上層部から見て、成果を出している上司のマイナス面を見極めることは難しい面があります。そこでまずは、社内に「部下を潰す上司」が本当にいるのかを確認していきましょう。
部下を潰す上司の有無を確認するには、社内アンケートを実施する方法が有効です。アンケートの記入者を匿名にすれば、普段は訴えにくい些細なことでも書きやすくなり情報を集めやすくなります。
匿名で相談できる窓口を設置
こちらも部下を潰す上司の存在を浮き彫りにするために必要な対策です。何より部下を潰す上司の問題点は、部下という被害者が出ている・人材流出のリスクがある点です。
上司本人の問題点を対策することも大切ですが、まずは被害に遭った部下の保護やケアが重要になります。被害者一人に我慢を強いれば、耐えきれなくなって退職してしまうケースが増えます。このようなことにならないよう、早急に相談できる場を設けましょう。
定期的な研修も有効
実際に社内に部下を潰す上司がいると判明した後は、上司本人の意識改革が必要です。また部下を潰す上司の中には、育成の気持ちはあるが間違った育成方法を正しいと思い込んでいるケースもあります。
これらを改善するには、定期的な研修などを用い、適切な指導とはどのようなものなのかを上司自身に知ってもらうことが大切なのです。
部下育成はもちろん、経営陣目線を持つには専門的な知識を学ぶことが必須になります。研修やセミナー、異業種交流、1on1などさまざまな方法を使って部下を潰す上司に学んでもらいましょう。
まとめ
部下を潰す上司には以下のような特徴がみられます。
- 共感性が低く鈍感
- 自分が正しいと思っている
- 仕事に私情を挟みやすく感情的
- 仕事はできるor要領がよい
基本的に他者に厳しいところが多く、人間関係における柔軟性が低い傾向があります。部下を潰す上司を放置しておくと、優秀な人材の流出を許すことにもなりかねないため、できるだけ早急に手を打つことが大切です
社内アンケートの実施や相談窓口を設けるなど、部下を潰す上司の存在を明らかにすることはもちろん、肝要なのは上司自身の意識改革。部下を正しく育成することが上司の役割であるなら、管理職の成長を促すのは企業や経営陣の責務です。
ただ、日々忙しい経営陣が個人の成長を促すために自ら動くことは難しいでしょう。そこでおすすめになるのは、人材育成の専門家に頼ることです。
管理職の成長は企業の次世代を担うためにも非常に大切なポイント。当社では若手はもちろん、次世代経営者を対象に考え方・実践力を高めるレベルの高い講座を開催しています。ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。