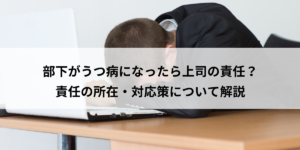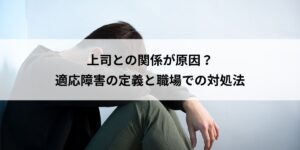こんにちは!栗原誠一郎です。
新入社員の「志」
弊社が毎年主催している異業種交流型合宿研修「新入大卒錬成講座」で、ある受講生が、研修最終日に作成した企業人としての自らの志をまとめた論文を、「死ぬ気で生きていきたい。」と結んでいました。
この論文を読んだ時は、単に、「これから頑張るぞ」という気合を表したものくらいに考えていました。
しかし、その後、彼の愛読書を聞いて、単なる気合ではないことが分かりました。
彼の愛読書は哲学者ハイデッガーの名著「存在と時間」だったのです。
20世紀最大の哲学書「存在と時間」
西洋哲学の世界では、古来、「存在」について探求してきました。
「いったい何が『ある』のか?」というように「存在している対象」を認識しようとしてきた訳です。
しかし、ハイデッガーは、その著書「存在と時間」の中で、「我々は、『ある』という言葉の意味が何を意味しているかという問いに答えをもっていない」と言って、これまで「ある」という事を自明な概念としてきたそれまでの西洋哲学を批判しました。
それまでの西洋哲学において「ある」とは何かが「目の前に見出されること」と理解されていましたが、「ある」とは必ずしもそのように理解できるものだけではないと彼は言います。
その分かりやすい例が人間です。
確かに人間も「二足歩行の動物」のように事物として扱うことも可能ですが、人間は例えば私とあなたが違うように、それぞれが違う存在であるわけです。逆に、この他者と異なることこそが、人間という存在の核心をなしていると言えるでしょう。したがって、目の前に見出される事物のような捉え方では、人間という「存在」を規定できない訳です。
そしてハイデッガーは、「存在の意味」を明らかにするためには、あらゆる存在を規定する私たち自身、この「人間」という「存在」を分析する必要があるとして、探求を行います。
人間という存在の本質
それでは人間の存在とはいったいどのようなものでしょうか?
人間は時間の流れの中で、周囲(世界)との関係を常に持っており、そして、その都度その都度自己のあり方を選択しています。これこそが「人間」の「個別性」であり、この都度の「あり方の選択」こそがその人間の「存在」を規定していると言えるのです。
一方、人間は周囲との関係性の中でしか自己を規定できないために、逆に、周囲との差異に意識が向きやすくなります。そのために、人間は、自分がその時々に直面している状況において何をなしうるか、つまり「自分の」あり方を選択できるにも関わらず、そこに「周囲との差異」を感じると、居心地の悪さを感じ、「世間的」な「あり方」を選択し、他者と変わらない「あり方」に埋没していくのです。
では「世間的」な「あり方」ではなく、自分としての「あり方」を選択するためには、何が必要なのでしょうか?
それは、「死」を自分の事として考えることです。
私たちは普段、他人の「死」を外側から見ているだけで、自分は「死」を経験していません。
人間の存在は死によって完結します。だから、この死という終わりこそが、人間の全体を境界づけ、人間という存在の「全体性」を明確にします。
すなわち、死を「他ならぬ自分自身の」事として受け入れるとき、自分という存在の意味を理解し、「世間」と訣別し、独自の道を歩むことを選択するようになるのです。自分が「死へ向かう存在」であることを直視できたときに、絶望から希望へと進むことができるのです。
主体的に生きる
冒頭に紹介した新入社員はその論文の中で、まだ世間もよく知らない今の自分を受け入れ、周りから多くのものを吸収しつつ、一方で自分の価値観というものを大切にしていきたいとの想いを述べていました。
ハイデッガーも、死を受け入れることで「世間と訣別する」ということは、人間が事物や他者から完全に切り離されるということではなく、また、おのれの関心をただ漫然と世間(一般論)によって規定された状態にとどめておくのでもなく、「自分が本来なすべきこと」という観点から自分の責任のもとに選びなおすようになるということだ、と述べています。
そもそも人間が生きているこの世界を無視して、自分勝手に生きることなどそもそもできませんし、逆に死を受け入れることでこそ、より良い共存を生むことができるようになるのです。
人間が自分の死を受け入れなければ、人間は自己保存に固執し、己が関わる対象(人間や自然など万物)を自己保存のための有用性という視点でしかとらえられなくなります。
現代社会における環境破壊や社会の閉塞感も、このような自己保存への固執が原因といって良いでしょう。
昔、「一休さん」の愛称で有名な室町時代の臨済宗の僧一休宗純の話で、正月にどくろを掲げて街をあるく話がありましたが、この話にも共通する考え方がありますね。
さて、あなたは「死ぬ気で生きている」と言える「あり方」で、今、生きているでしょうか?